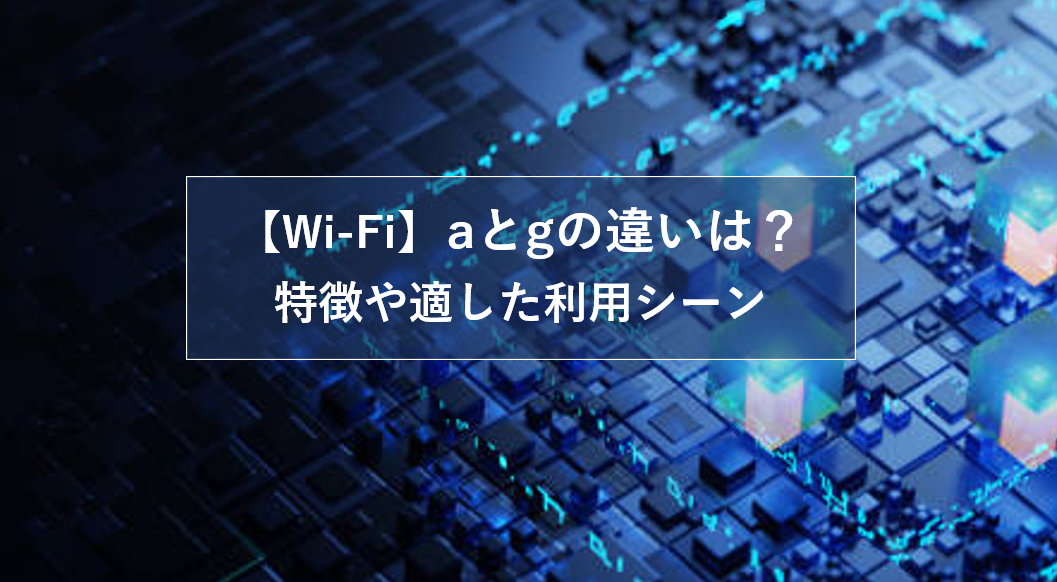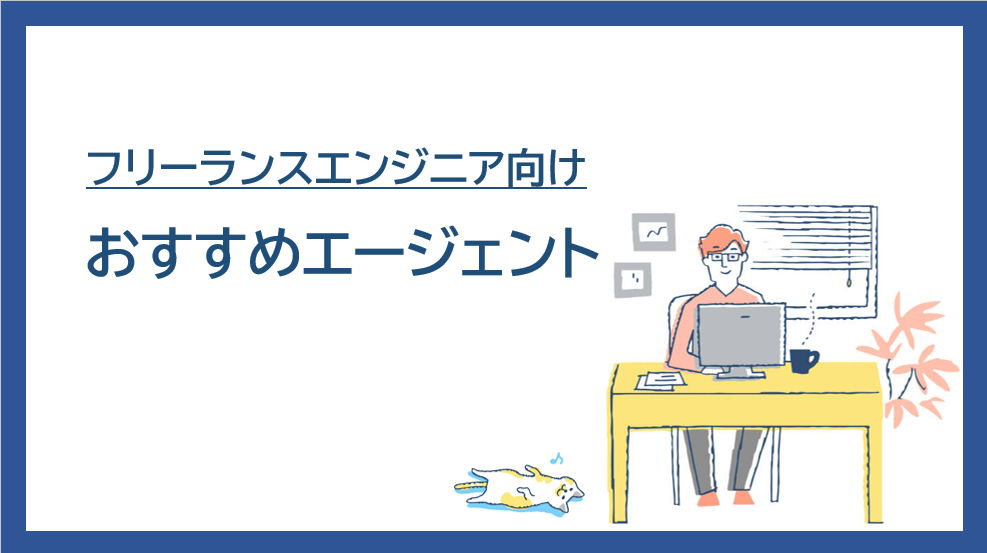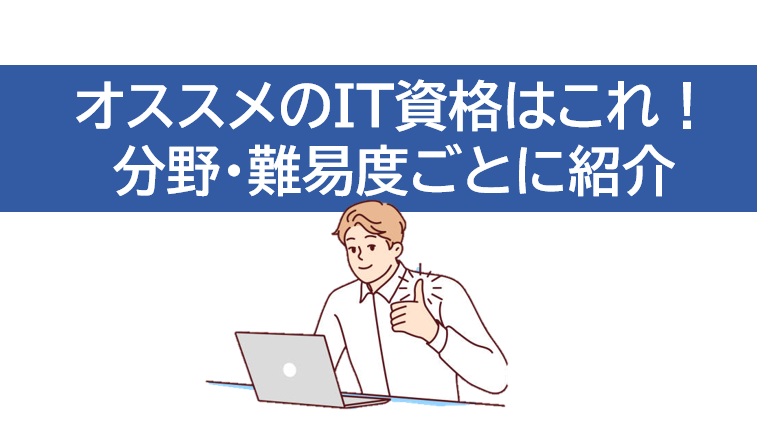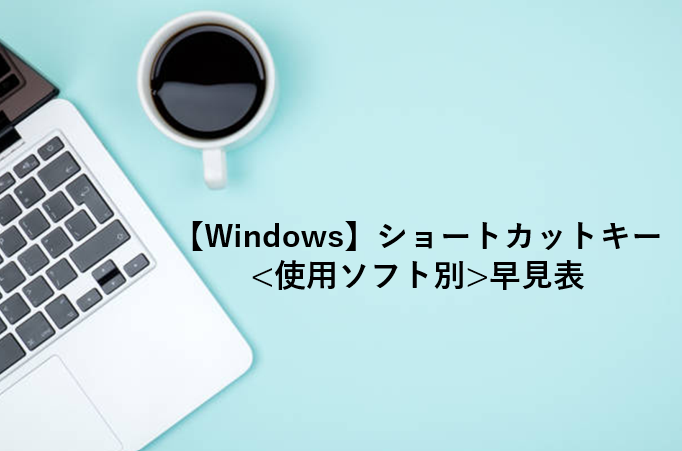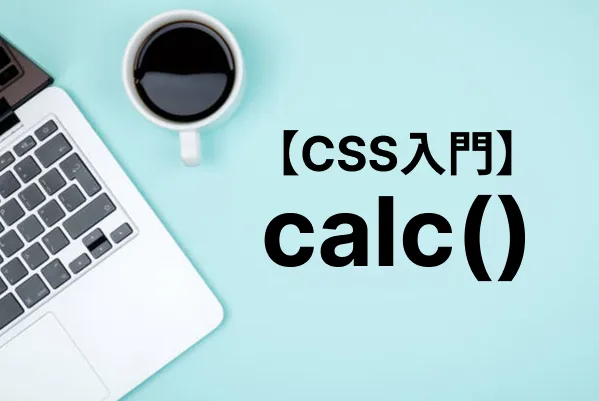インターネットを利用する際に、Wi-Fiに接続する人も多いのではないでしょうか。Wi-FiのSSID(Wi-Fi通信に利用するネットワークの識別名)に「a」と「g」の2種類が存在する場合があります。そこで本記事ではそれぞれ特徴と適した利用シーンを中心に解説します。両者の違いを理解し、より快適にWi-Fiを利用しましょう。
Wi-Fiのaとgの意味
Wi-Fiとは、「Wireless Fidelity」の略で、無線(ワイヤレス)でデバイスをネットワークに接続する無線LANの通信規格の一つです。Wi-Fiの利用には電波をデバイスに届けるルーターが必要です。Wi-Fiを利用することでPCやスマートフォン、テレビなどのさまざまな機器でインターネットを利用できるようになります。
Wi-Fiルーターによっては、周波数帯の違いによって「a」と「g」の2種類のSSIDに分けられ、各周波数帯は次のようになります。
a:5GHz帯
g:2.4GHz帯
Wi-Fiの「a」と「g」にはそれぞれ異なる特徴があり、その特性に合わせて使い分けることで快適な通信環境を築けるでしょう。
Wi-Fiのaとgの違い
Wi-Fiの「a」と「g」では、使用する周波数帯が違います。周波数帯のそれぞれ特徴を以下に示します。
a(5GHz帯)の特徴
Wi-Fiが登場時から利用されてきたスタンダード規格である2.4GHz帯に対して、5GHz帯は規格のバージョンアップの過程で利用されるようになった通信規格です。ちなみに、「5GHz」と「5G」は別物です。
5GHz帯の長所
5GHzはWi-Fi専用の周波数帯であり、基本的にルーター以外で利用されることがないので、その分ほかの機器と電波干渉の心配が少なく、2.4GHzに比べて速度が速く安定した通信が可能です。そのため、日常的に複数の機器を使用している場合や集合住宅住まいの人におすすめできます。
また、後ほど詳しく説明しますが、最大通信速度は基本的に5GHz帯のほうが2.4GHz帯よりも速いので、動画やオンラインゲームのように通信速度が求められる場合は5GHz帯を利用するのがおすすめです。複数のデバイスを同時に接続しても、そんなに速度の遅延は起こりません。
5GHz帯の短所
5GHz帯は技術的にも新しく、基本的には2.4GHz帯よりも優先して利用する方がいいケースが多いです。ただ、5GHz帯は2.4GHz帯よりも電波の届く距離が短いのでルータから離れた位置では通信が不安定になりやすいです。戸建てやオフィスなどの広い場所での使用や壁や階数をまたぐ使用には不向きです。それでもる買いたいという場合は電波が届きやすい場所にルーターを配置したり中継機を使用するなどして対応しましょう。
また、5GHz帯は障害物・遮蔽物に弱く、2.4GHz帯に比べて電波の届く距離が短いので壁や家具など、遮蔽物が多いと電波が弱まり、通信が不安定になり2.4GHz帯に劣ります。
ほかにも、デバイスによって対応する周波数帯が異なると説明しました。5GHz帯に対応する製品が増えつつも、すべてのデバイスに対応しているわけではないということにも注意が必要です。特に古いデバイスには未対応のものが多いです。Wi-Fiのa(5GHz帯)を利用する場合は、5GHz帯に対応しているか事前に確認しましょう。
g(2.4GHz帯)の特徴
2.4GHz帯はスタンダード規格として広く普及している周波数帯です。
2.4GHz帯の長所
2.4GHz帯は、5GHz帯と比べて周波数が低いため、電波が遠くまで届きやすいという特徴があります。つまり、Wi-Fiルーターの位置から離れた場所でも通信ができるということです。また、壁や床、家具などの遮蔽物にも強いので、ルーターのある部屋と壁を挟む部屋や天井や床を挟む階上・階下の部屋にも問題なく電波を利用できます。
ほかにも、2.4GHz帯は、Wi-Fiが登場時から利用されてきたスタンダード規格であるため、基本的にはWi-Fiを利用するデバイスに対応しているので互換性を気にしなくて済みます。古い規格でも利用されている周波数帯であり、多くの端末に対応しています。
2.4GHz帯の短所
長所に「対応機種の多さ」を挙げましたが、これは短所としても作用します。Wi-Fiに限らず、電子レンジやBluetoothなどといった、多くの家電製品や電子機器で利用されている周波数帯であり、ほかの機器との電波干渉が起こりやすく、電波が弱まることで通信速度の低下や通信切断が起きやすいです。たとえば、ルーターの近くで電子レンジのような強い電波を発する家電を使用した場合、互いに電波が干渉して、通信速度が遅くなったり通信が途切れたりする可能性があります。データサイズの大きいアプリなどをダウンロードしたり動きの多いオンラインゲームをストレスなく楽しみたいという場合は不向きといえます。
また、遮蔽物にも強いことで、特にマンションやアパートなどの集合住宅では隣の部屋や上下階の部屋との電波干渉が起こる可能性もあり、通信が不安定になることもあります。ただ、障害物を考慮しないと通信速度は5GHz帯に劣ります。
| 2.4GHz | 5GHz | |
| 長所 | ・電波が遠くまで届く ・遮蔽物の影響を受けにくい ・多くのデバイスに対応している | ・電波干渉が起こりにくい ・通信速度が速い |
| 短所 | ・電波干渉が発生しやすく通信速度が不安定になりやすい ・通信速度は5GHz帯に劣る | ・電波の届く範囲が狭い ・遮蔽物の影響を受けやすい ・対応していないデバイスがある |
Wi-Fiの通信規格によってどちらを使えるか決まっている
Wi-Fiは通信規格によって、a(5GHz帯)とg(2.4GHz帯)のどちらが利用可能か決まっています。ルーターごとに利用可能な通信規格が異なります。そして、その通信規格によって周波数帯と通信速度が異なります。周波数帯の使い分けをするうえで知っておくべきことなのでぜひチェックしておきましょう。
Wi-Fiは「IEEE 802.11(アイトリプルイー)」という国際規格で周波数帯や通信速度が定められています。「IEEE 802.11」には下記のようにさまざまな種類があります。
| Wi-Fi規格名 | 最大通信速度 | 周波数 | 名称 |
| IEEE 802.11a | 54Mbps | 5GHz | – |
| IEEE 802.11b | 11Mbps | 2.4GHz | – |
| IEEE 802.11g | 54Mbps | 2.4GHz | – |
| IEEE 802.11n | 600Mbps | 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 4 |
| IEEE 802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz | Wi-Fi 5 |
| IEEE 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 |
| IEEE 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz/5GHz・6GHz | Wi-Fi 6E |
現時点での最新の通信規格は最大通信速度が9.6Gbpsの「IEEE 802.11ax」であり、2.4GHz、5GHzに加えて、6GHzの周波数帯も利用できます。最も普及しているの通信規格は「IEEE 802.11ac」ですが、「IEEE 802.11ax」はその最高速度の約1.4倍となっています。
aとgの使い分けのポイント
Wi-Fiのa(5GHz帯)とg(2.4GHz帯)は使い分けるのが有効です。
まず、a(5GHz帯)が適したケースを紹介します。
a(5GHz帯)
複数の電子機器を使用するとき
複数の機器を使用する場合は、伝播干渉のしにくいa(5GHz帯)がおすすめです。情報処理学会の実施した試験では2.4GHzは12台までであるのに対し5GHzは30台まで同時接続が可能だという結果が出ました。ただし、ルーターによっても異なるので仕様を確認しましょう。また、集合住宅の場合も電波干渉を防げるので通信が安定しやすいです。
動画の視聴やゲーム利用時
a(5GHz帯)は、gと比較して通信速度が速く、電波干渉も受けにくいので通信が安定しやすいです。そのため、動画視聴やオンラインゲーム、ビデオ通話などの、大容量のデータをやり取りし、一定の通信速度や安定性が必要な場合はaがおすすめです。ただし、障害物・遮蔽物に弱いのでルーターから距離が離れると不安定になってしまいます。
g(2.4GHz帯)
ルーターから離れた場所や別の階から接続するとき
gは遮蔽物・障害物に強くて電波の届く範囲が広いので、ルーターから離れた位置や家の中であちこち移動しても安定して利用しやすいです。ただし、ほかの機器と電波干渉を起こしやすい点には注意が必要です。
海外製や古い製品に接続するとき
海外製の製品や古い製品はaに対応しておらず、接続設定時にSSIDの表示一覧にもaが出てこない場合があります。その場合はgに接続しましょう。
| 2.4GHz | 5GHz | |
| 利用環境・利用シーン | ○家電製品や電子機器をそんなに使っていない ○ルーターと距離がある ○遮蔽物越しに通信を行う ○戸建て | ○ほかの機器と干渉させたくない ○ルーターの近くにある ○遮蔽物が少ない ○集合住宅 |
表を参照すると2.4GHz帯よりも5GHz帯の方が通信速度が速いのがわかります。安定して通信できるので基本的に5GHz帯を使用するのがおすすめです。しかし、ルーターから距離が離れている場合や遮蔽物が少ない場合は2.4GHz帯の方が安定する場合があります。ただ、そもそもルーターが5GHz帯に対応していない場合は必然的に2.4GHz帯を利用することになります。電波干渉に注意しましょう。
このように、利用環境や利用シーンによって適した周波数帯は変わるのでそれそれの長所と短所を考慮して電波が安定し、より速いほうに接続しましょう。まずは5GHz帯に接続してみて通信が不安定な場合は2.4GHz帯に接続してみることをおすすめします。なお、ルーターがどの規格に対応しているかも製品情報などから調べる必要があります。
また、いずれかの周波数帯が混雑している場合に、もう一方の周波数帯に接続すると通信が快適になる場合もあります。
注意点
Wi-FiのaはDFSの制限を受けるケースがある
g(2.4GHz帯)は、気象レーダーや航空機レーダーといった、レーダー波にも利用されています。レーダー波はWi-Fi電波よりも重要度が高いので、干渉を避けてルーターにDFS機能が備わっています。DFS(Dynamic Frequency Selection)とは、レーダー波を検出すると5GHz帯のWi-Fi電波が停止される機能です。aは通信速度が速く、安定性も高いですが、DFS制限を受ける可能性があるという点は留意しておきましょう。
2.4GHzと5GHzは同時通信できる?
ここまでの説明で両者を同時に使うことができないか疑問に思った人もいるのではないでしょうか。両者のいいとこどりをできたらいいですが、実際には1つの端末で同時に複数のネットワークは使用できません。現在販売されているルーターの大多数は2.4GHzと5GHzの両方の周波数帯に対応しており、親機であるルーターでは2.4GHz帯と5GHz帯を同時に発信できます。
しかし、ルーターが複数の周波数帯を発信できても、受信する端末側では1つの電波しか受け取れられないため、2.4GHzと5GHzのいずれか選ばなくてはなりません。ただし、スマホは5GHz帯、PCは2.4GHz帯につなぐといったように、端末ごとに使い分けることはできます。
aとg両方とも接続できない場合の対処法
ルーターと各機器を再起動する
ルーターや各機器は長期間稼働させると不具合が生じる可能性があります。再起動すると改善する場合があります。電源オフ後1分後に再度電源を入れましょう。再起動方法は機器によって異なるので仕様を確認しましょう。
通信会社に問い合わせる
Wi-Fiが繋がらない場合は、通信会社側で問題が起きている場合があります。特定の機器だけではなく、複数の機器で繋がらない場合は通信会社に問い合わせてみましょう。
aまたはgに接続できない場合の対処法
機器が周波数帯に対応していないケースである場合があります。周波数帯に対応するWi-Fiアダプタを機器に繋げて使用できます。各機器の仕様を確認してください。
Wi-Fiが頻繁に切れる/通信速度が遅い場合の対処方法
接続するSSIDの変更
安定した通信を行うために適切なSSIDを選ぶ必要があります。接続するSSIDを選択して接続しましょう。
ルーターやWi-Fi中継機の設置場所を変更する
ルーターや中継機の設置場所を変更すると改善する場合があります。
- 床から1~2mの高さに設置する
- なるべく家の中心部に設置する
- 水回りや湿気の高い場所の近くは避ける
- 電子レンジ・Bluetooth機器などの近くは避ける
- 金属製の棚に置くのは避ける
- 中継機をWi-Fiルーターに近づける
ルーターのスイッチ切り替え
ルーターのスイッチを変更すると改善する場合があります。機器の「ルーター機能あり/なし」を確認します。判断しかねる場合は提供元に問い合わせましょう。
ファームウェアの更新
最新版のファームウェアにアップデートすることで、機能性が向上するほか、不具合が解消される場合があります。
インターネット接続の手動設定
インターネット通信が原因である場合は、ルーター内の設定を変更することで改善する場合があります。
DNSサーバアドレスの固定
ルーター設定を変更することで改善する場合があります。変更後に機器をルーターに再接続してインターネットに接続できるか確認しましょう。
無線チャンネルの変更
ほかの無線機器と干渉して無線チャンネルの通信が不安定になっている可能性があります。無線チャンネルを変更しましょう。
Wi-Fi端末のIPアドレス固定
IPアドレスの自動割当て(DHCP)が機能していない可能性があるためIPアドレスを固定して異なる値に変更しましょう。
中継機の設置
中継機の使用を検討しましょう。中継機とは、Wi-Fiの電波の届く範囲を拡げる機器です。ルーター本体を移動せずに済みます。中継器以外にもメッシュWiFiに対応する機器を利用する方法があります。メッシュWi-Fiとは、複数のノード(ルーターと同様の性能を持つ機器)を電波を網目状につなげて1つのネットワークとする通信形態です。電波が不安定になる地点を迂回して通信できるのでルーターから距離があったり遮蔽物がある場合でも通信が安定します。広い家や、複数階数がある場合に有効です。
周波数帯の切り替え方
ではその切り替えはどのように行えばいいのでしょうか。接続の切り替えは、端末上の設定で接続をし直すことでできます。
なお、接続にはネットワーク名(SSID)とパスワードが必要になります。ルーターの背面や底面などに記載されているコードを確認しましょう。
SSIDに「a」・「g」がつく場合は、「a」が5GHz帯、「g」が2.4GHz帯になります。ほかの名称で設定されている場合もあるので製品の説明書を参照してください。なお、後述する周波数帯の自動切り替え対応機能のあるルーターの場合は、基本的はSSIDが統一されている場合が多いです。
Wi-Fiの接続手順
Wi-Fiの接続手順は下記のとおりです。別のことで、それまで接続していたネットワークが切断されてネットワークが切り替わります。
▼iPhone・iPadの場合
- 「設定」>「Wi-Fi」を選択する
- Wi-Fi機能をオンにする
- ネットワーク一覧から接続するSSIDを選択する
- パスワードを入力して接続する
▼Androidの場合
- 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「インターネット」を選択する
- Wi-Fiをオンにする
- ネットワーク一覧から接続するSSIDを選択する
- パスワードを入力して接続する
【おまけ】周波数帯自動切り替え機能
現在販売されているルーターの大多数は2.4GHzと5GHzの両方の周波数帯に対応しており、機種によっては接続状況を見て端末ごとに最適な周波数帯に自動で切り替える機能を搭載しています。ネットワークの再選択といった手間が省けて便利な機能です。ルーターの購入を検討している人は基本スペックに加えてこの自動の切り替え機能の有無もチェックするといいでしょう。
ITスキルの習得方法は?
書籍やインターネットで学習する方法があります。昨今では、YouTubeなどの動画サイトやエンジニアのコミュニティサイトなども充実していて多くの情報が手に入ります。
そして、より効率的に知識・スキルを習得するには、知識をつけながら実際に手を動かしてみるなど、インプットとアウトプットを繰り返していくことが重要です。特に独学の場合は、有識者に質問ができたりフィードバックをもらえるような環境があると、理解度が深まるでしょう。
ただ、ITスキルを身につける際、どうしても課題にぶつかってしまうことはありますよね。特に独学だと、わからない部分をプロに質問できる機会を確保しにくく、モチベーションが続きにくいという側面があります。独学でモチベーションを維持する自信がない人にはプログラミングスクールという手もあります。費用は掛かりますが、その分スキルを身につけやすいです。しっかりと知識・スキルを習得して実践に活かしたいという人はプログラミングスクールがおすすめです。
プログラミングスクールならテックマニアがおすすめ!

ITスキル需要の高まりとともにプログラミングスクールも増えました。しかし、どのスクールに通うべきか迷ってしまう人もいるでしょう。そんな方にはテックマニアをおすすめします!これまで多くのITエンジニアを育成・輩出してきたテックマニアでもプログラミングスクールを開講しています。
<テックマニアの特徴>
・たしかな育成実績と親身な教育 ~セカンドキャリアを全力支援~
・講師が現役エンジニア ~“本当”の開発ノウハウを直に学べる~
・専属講師が学習を徹底サポート ~「わからない」を徹底解決~
・実務ベースでスキルを習得 ~実践的な凝縮カリキュラム~
このような特徴を持つテックマニアはITエンジニアのスタートラインとして最適です。
話を聞きたい・詳しく知りたいという方はこちらからお気軽にお問い合わせください。
【Wi-Fi】2.4GHzと5GHzの違い・使い分け